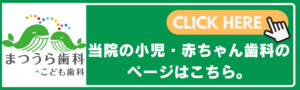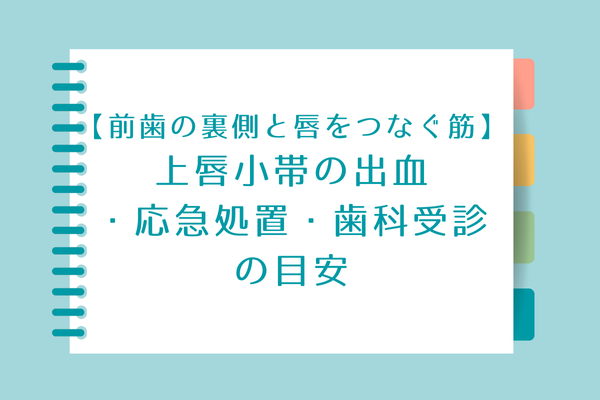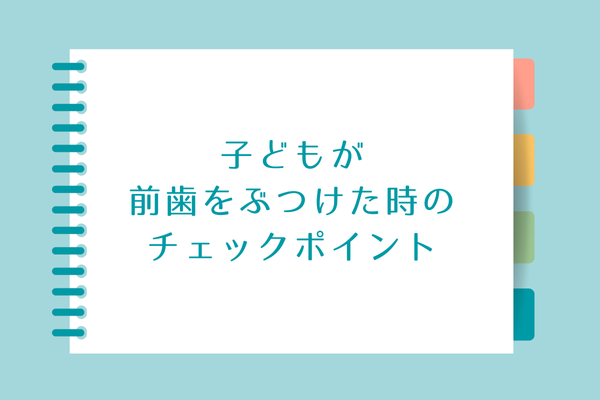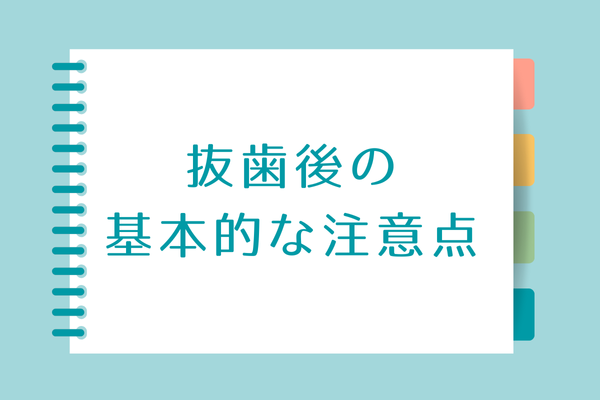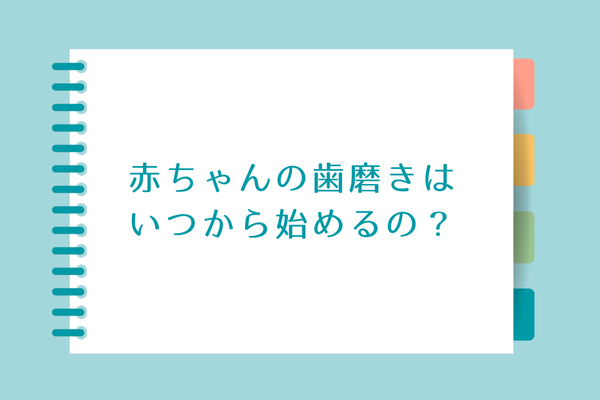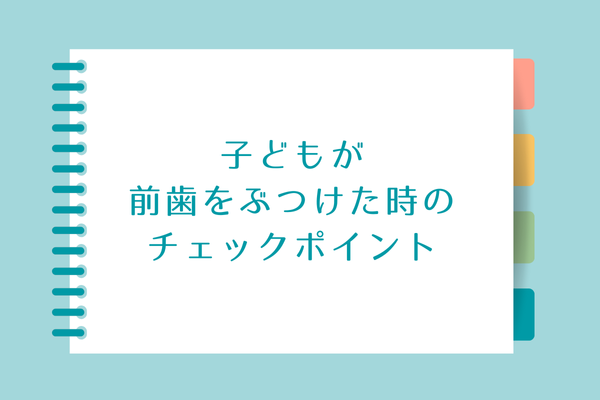目次
1. はじめに
小児歯科の局所麻酔は、安全性が高く痛みもほとんどありませんが、「しびれが残っている間にくちびるや頬を噛んでしまう」 アクシデントは珍しくありません。噛んだ直後は痛みを感じにくいものの、数時間後に腫れや血豆が目立ちはじめると、保護者の方はとても心配になります。本記事では、家庭で今すぐできる応急処置、医療機関を受診すべきサイン、再発防止のコツ を詳しく解説します。
2. なぜ噛んでしまうのか?
-
麻酔による感覚低下
術後2〜3時間は触れても「触れている感覚」がほぼありません。
-
違和感を確かめようとする行動
「腫れている?」「虫がいる?」という好奇心から、無意識に噛んでしまうことがあります。
-
集中力の途切れ
遊びや動画に夢中になり、口の中の異変に気づきにくい傾向があります。
-
お腹が空いてすぐ食べる
麻酔が切れる前に食事をすると、誤って噛むリスクが急上昇。
3. 症状チェックリスト
| 程度 | 目で見える変化 | お子さまの様子 | 自宅ケア | 受診の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 軽度 | 白っぽい跡のみ | 触ると少し痛い | 冷却・清潔保持 | 次の日に腫れが増すなら受診 |
| 中等度 | 赤く腫れる・軽く出血 | ひりひり痛む | 冷却+鎮痛薬 | 24時間で腫れが引かなければ受診 |
| 重度 | 紫〜黒の血豆・裂傷 | 泣く/食事困難 | 応急処置後すぐ受診 | 当日中に歯科 or 口腔外科 |
4. 応急処置
安心させる
「大丈夫、噛まないように気を付けようね」と優しく声を掛け、お子さまの不安を軽減します。
冷却する(10〜15分)
清潔な保冷剤をガーゼで包み、くちびる外側から当てます。冷やす → 5分休む → もう一度冷やす、を2セット。
止血・洗浄
滅菌ガーゼで軽く圧迫し、ぬるま湯や生理食塩水でやさしくうがい。アルコール系洗口液は刺激が強いので避けましょう。
鎮痛薬の使用
体重に合わせたアセトアミノフェンを推奨。イブプロフェンは空腹時NG。服用前に必ず用量を確認してください。
柔らかい食事と水分補給
しみる柑橘や塩分の強い食品は避け、プリン/ポタージュ/おかゆなどを少量ずつ。
5. 受診が必要なサイン
-
出血が20分以上続く
-
傷の長さが5 mm以上、または裂け目が深い
-
24時間後も腫れが拡大、あるいは熱感・発熱が出てきた
-
飲食がほぼできない/痛みで眠れない
これらに当てはまる場合は、迷わず歯科医院または口腔外科へ。傷が深いと縫合が必要になるケースもあります。
6. 治癒までのホームケアのコツ
-
触らない・いじらない
→ 舌や指で触ると治りが遅れ、細菌感染のリスクも増加。 -
保湿ケア
→ ワセリンやプロペトを1日3回、薄く塗り乾燥を防止します。 -
バランスの良い食事
→ ビタミンB群・Cを含む食材(ささみ、ブロッコリー、いちご)を摂ると粘膜修復がスムーズ。 -
十分な睡眠
→ 成長ホルモンの分泌で組織修復が促進されます。 -
経過観察メモ
→ 腫れの写真を毎日同じ時間に撮影し、変化を記録すると受診時の情報共有に役立ちます。
7. 再発防止の3つのポイント
-
しびれが取れるまで食事を控える(目安3時間前後)
-
無意識防止にガーゼを噛ませる
「ガーゼを噛んでいれば安全」と教えておくと、噛傷を大幅に減らせます。
-
保護者が30〜60分見守る
特に幼児は感覚異常を言語化できないため、そばで様子を観察しましょう。
8. よくあるQ&A
治るまでの期間は?
軽度なら2〜3日、中等度は1週間前後、深い裂傷だと2週間以上かかることもあります。
学校や保育園は休ませたほうがいい?
食事と会話が支障なく行えれば登校OK。ただし体育や激しい遊びは腫れが治まるまで控えめに。
市販の軟膏は使ってもよい?
口腔内専用のもののみ使用可。皮膚用ステロイド軟膏は絶対に塗布しないでください。
9. まとめ
-
冷却・清潔保持・早期止血 が初期対応の鍵。
-
腫れや痛みが強い場合は迷わず受診、早期治療で治癒を早めます。
-
しびれが残る時間を親子で共有 し、見守りと食事制限で再発を防止しましょう。
お子さまのお口のトラブルは早期対応ほど回復が早くなります。気になる症状や不安がある場合は、いつでも当院までご相談ください。
赤ちゃん歯科、小児歯科、小児矯正に関してのお悩みは
住吉区の歯医者
まつうら歯科・こども歯科までご相談ください。
赤ちゃん歯科外来(0〜2歳)のご予約は水曜日17時までと土曜日の13時までとなっております。
小児歯科のご予約は全ての診療日でご予約が可能です。
小児矯正のご予約は、お電話でお問い合わせください。
write:2025.5.17